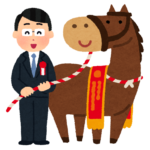この春、発達障害がある息子が就職してまる2年経ち、4月からは社会人3年目なりました。
今では当たり前のように毎朝仕事に出かけていきますが、高校生活まで、就職が決まるまでは「ちゃんと社会に出れるのだろうか」「就職できるんだろうか」と不安をたくさん抱え、試行錯誤しながら子育てをしてきました。
今回はそんなさまざまあった学校時代を経て息子が就職するまでにやってきたことで良かったこと、反対にもっとああしておけばよかったという反省点をまとめてみました。
発達障害がある小さいお子さんを育てているご家族、就職のため、社会に出るために頑張っていられるご家族に参考にしてもらえることがあればうれしく思います。
発達障害の息子が就職。これまでを振り返って

1.息子の概要
現在20歳です。
1歳半の健診時に発語の遅れ、多動、こだわりの強さなどを指摘され、軽度知的障害、自閉症スペクトラムと診断されました。
療育センターから小中学校は普通校の個別支援級、高校は養護学校系の分教室に通いました。高校での企業実習を経て卒業後は民間企業の特例子会社に就職することができました。
特性として言葉で伝えること、相手の話を理解することは小さい頃から力が弱く、社会に出た今でも苦労しています。
また、相手の気持ちに配慮する、相手を気遣うといったことも苦手。抽象的な表現や隠し事をすることはできません。ストレート過ぎてトラブルになったり、相手を怒らせてしまうことも少なくありませんでした。
一方でこだわりの強さという課題は少しずつ継続力という長所にもつながっていきました。企業実習でもその長所が評価され、追実習という再チャレンジの機会をつかみ、就職に繋げることができました。
なかなか解消できない課題もたくさんあれば、時間はすごくかかるけど少しずつ軽減していったり、秀でた強みも見つかったりといろいろありながら半歩ずつ前に進み就職につながったという感じです。
2.これまでやってきたなかで良かったこと

できる限りいろいろなことを経験させてきた
本人がやりたいと言ったこと、興味を示したことはほとんどやらせてきました。
そのことで息子の可能性や感受性が広がり、普段穏やかに生活できることにつながり、社会と接する訓練の機会になったと感じています。
例えば息子には下記のようなことを経験させてきました。
- ディズニー英語システム
- 休日の公園めぐり
- トランポリン
- ハングライダー
ディズニー英語システムは発語の遅れもあったため英語からでも発語を促したいと思ったことがきっかけで始めました。期待したとおり英語での発語がすごく増え、意思表示をすることも増えていきました。
日本語の発語はあまり進みませんでしたが、その後ディズニーに関するいろいろな世界に興味を示すようになり、そのことを通じて息子の意識が外の世界へ向くきっかけになったと思います。
フル教材を購入したので安くはなかったですが、今でも教材は大事に取っていてたまに見たりしています。十分価値はあったかなと思っています。
休日の公園巡りはブランコ、すべり台大好きがきっかけで始まり、日曜日ごとに自転車で地域のいろいろな公園に毎週出かけていました。雨が降らなければ毎週欠かさず、真夏の暑い日も関係なく…。
親としては正直きつい部分もありましたが、日曜日は大好きな公園に行ってブランコ、すべり台で遊べるというサイクルが息子の中ででき、その満足感からその後の一週間は落ち着いて生活できるというリズムにつながっていきました。
また公園では他の子どもたちも遊んでいたので、ブランコ、すべり台の順番を待つ、他の子に譲るという社会のルールや他人との関わり方を少しずつ覚えるいい機会になったと思います。
トランポリンについても自閉症の子に多いと言われている跳ねる、飛ぶが大好きから始まり、療育センターや学校ではいつも跳んで遊んでいましたので、もっとやらせてあげたいと思いから近所の体操教室に通うようになりました。
一般の子供達と一緒に汗をかいて、時にはマイペースなことを他の子にいじられながら楽しそうに体を動かしていました。ここでも本人の好きなことをやりながら、集団行動や協調性などを身につけるいい機会になったと思います。
そしてハングライダーについてはディズニーの世界から空を飛ぶということに憧れを持ち「跳ぶ」が「飛ぶ」に発展したようで、「空を飛びたい」と言い出したため経験させました。
そんな感じで本人がやりたいと言ったこと、興味を示したことは時間とお金が許す範囲でほぼ経験させてきました。
それで何か遅れを補えたということが明確にあるわけではないですが、限りがありがちになる世界を少しでも広げ、社会との接点を増やすという意味ではとても重要だったと思います。
ハンディがあるぶん、より多くの経験をさせてあげる、過ごす時間をできるだけ濃いものにしてあげることはすごく大事だと思います。
夫婦で関わってきた
夫婦で協力して関わってきました。
共働きでしたので協力せざるを得ないこともありましたが、学校に関すること以外にも息子に関することは夫婦で役割分担して対応してきました。
その効果か、まずは息子が穏やかでやさしい人柄で育ってくれたました。もともとの性格もあるとは思いますが、学校の先生から「本人の普段の様子でご両親の愛情をたくさん受けているのがよく分かります」と言われ、そうなんだなと実感しました。
自分達はあまり意識したことはありませんでしたが、息子の安心や気持ちの安定につながっていたのかもしれません。
また夫婦で協力することで学校行事やその他息子に関するいろいろな予定に参加して夫婦それぞれの目で息子の様子を見ることで、その様子を踏まえた意見交換ができたこともよかったと思います。
お互いに協力することで負担やストレスの軽減となり、結果的に夫婦が穏やかな気持ちで息子に接する時間も増えました。
自閉症の子は特に敏感に両親、家の空気を感じます。家庭ができるだけ落ち着いた環境であることで子供は落ち着いて過ごせ、それがその子が成長していくうえでの人柄につながっていくのだと思います。
学校行事にはフル参加
学校行事には可能性な限り参加してきたことも非常によかったと思います。
夫婦、そして両祖母などの協力も得ながら学校に関する予定はほぼ参加してきました。オープンスクール、運動会、文化祭はもちろん、他の行事も。
そうやってしっかり関わってきたことで良かったと思うことは数多くありました。
- ①学校での子供の様子の把握度が上がる
- ②先生とのコミュニケーションが密になる
- ③学校、先生への提案、意見がしやすくなる(良い意味で対等の関係をつくれる)
- ④学校、先生に緊張感を持ってもらえる
など。
特に③と④については、小学校時代に担任の先生のことでいろいろ学校と議論をすることになったため、すごく重要だったと感じています。
校長、教育委員会、議員さんなどとやりとりをした際に、より具体的な状況を踏まえた話や資料の提示に生きました。
学校に密に関わり、状況をしっかり把握することは子供の将来に向けて先生とより良い協議ができることにつながると思います。
また場合によっては子供を守るためにとても大事なことにもなると思います。
高校進学で無理しなかった
息子は高校受験の際に本命の学校に不合格となりました。
その時は息子もわたしも非常にショックでしたが、今となっては仕切り直してその後に進学した学校に行ったことは良かったと思っています。
他の受験生の言葉の力の水準がとても高く、仮に本命の学校に合格していたとしても正直「ついていけるかなと」と感じていましたので、息子のコミュニケーション力ではもしかしたら続けていられなかったもしれません。
背伸びをして本人の能力、性格に合わない身の丈以上の進学をしても、その後に無理が出でしまう可能性もあります。本人のリズムを乱さずコツコツ前進できる環境を選ぶことが、長い目で見た本人の成長にプラスになると思います。
進学に失敗しても無理せずその時の状態に合わせるのがベストです。
セミナー、講習などにも積極的に参加
学校から紹介のあったセミナーなどにも息子の将来のためになると思うものには積極的に参加しました。
特によかったと思うのが将来のお金に関するものでした。
学校時代はどうしても目の前の成長や学校生活、就職に向けてのことが優先になります。でも社会に出てからはお金についての自立、備えが欠かせなくなります。
障害基礎年金の制度についても高校2年の夏休みのセミナーに参加してはじめて知りました。
受給するためには申請が必要であること。また普段の困りごとの記録やかかりつけ医との継続接点も必要になることなど、セミナーに参加してなければ知ることができませんでした。
早めに知ったことで少しずつ準備や資料作りを進められ、年金受給につなげることができました。
3.反省点

どんどん失敗させることが足りなかった
これがいちばんの反省点です。
中学校の時の担任の先生に何度も言われてきました「今のうちにどんどん失敗させてください」と。でもやはり心配が先行し、親が決めたり口出し過ぎることが多かったと思います。
それにより自分で考える力が育たない、判断することができないということにつながってしまいました。社会人になった今でも、親離れ、子離れできていない関係が続いていることを感じます。
学校の準備、その日の服装、お金の使い方など、小さいうちからどんどんチャレンジさせてどんどん失敗する機会を作っておけばよかったと感じています。
親の過干渉をグッと我慢すること。親にとっても訓練です。
お金への関わりが足りなかった
お金に慣れさせていくことももっと早くやっておけばよかったという思っています。
息子は小学校の高学年くらいからお小遣いを始め、同時にお小遣い帳をつけさせ始めました。ただお小遣いを使って自分で買い物する機会を多く持たせなかったため、お小遣い帳の数字の計算が先行してしまいお金の価値や使い方の理解が進みませんでした。
実際にお金を使うという実践が足りませんでした。
今思うと一番やるべきだったのは買い物という実践だったと思います。買い物の中で実用的なお金の価値、使い方を体感で理解していくことをもっとやっておくべきでした。
理想は近所での買い物。近所であれば家族の見守りがあるなかで少しづつ練習でき、失敗してもフォローができます。「はじめてのお使い」形式です。
また店舗や近隣の人たちに顔を売れますし、子供のことを理解してもらう機会にもつながると思います。長くその地域に住んでいくのであれば将来に向けての本人のコミュニティを広げることにもつながります。
小さいうちから近所のお店でどんどん買い物をさせ、時には失敗をしながら生活のなかでのお金のことを覚えていく。
将来お金の扱いで困ったり、トラブルに巻き込まれたりするのを予防するためにも早めにお金に関わらせることはとても大事だと思います。
資産運用はしておくべき
成人するまでの20年近く、息子に関するお金を貯金に軸足を置いてきてしまったのも失敗でした。
低金利、そしてインフレがどんどん進む現代では貯金一本足ではお金の価値が下がり、塩漬けになる一方です。
障害がある子は社会に出ても収入の水準が低くなる可能性もあります。そういったことも考えて親がしっかりお金について勉強して株式投資などの資産運用を行い、子供の将来に向けて備えていくことが大事だと思います。
はじめは資金が小さくても子供が成人するまでに20年近くあり、時間というアドバンテージが最大限活用できます。
NISAなど優遇制度を使いながら、長期で得られる複利の効果を活用しない手はないと思います。
4.さいごに

自閉症の息子が就職。これまでを振り返って。
▪️良かった点
- できる限りいろいろな経験をさせてきた
- 夫婦で関わってきた
- 学校行事にはフル参加
- 高校進学で無理しなかった
- セミナー、講習などにも積極的に参加
▪️反省点
- どんどん失敗させることが足りなかった
- お金への関わりが足りなかった
- 資産運用はしておくべき
とりあえず就職して社会に出るというひとつの目標は実現しましたが、これからの息子の長い人生のなかで課題はまだまだあります。
今後の課題としては、
- お金の管理能力、資産運用の出口戦略
- 親なき後の息子の住まい
- 家事全般の自己管理力をつけさせること
- 親ができるだけ健康で長生きすること
- 地域コミュニティを維持し広げること
などがあるかなと考えています。
引き続き親としてこれらの課題に対して試行錯誤していきながら、息子の自立を目指して前進していきたいと思っています。
そんな中でまた皆さんのお役に立ててもらえるような情報があれば発信していきたいと思います。
障害があっても住みやすい世の中がもっともっと広がっていきますように。
最後までお読みいただきありがとうございました。